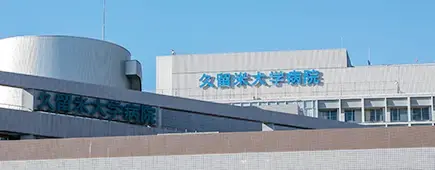- HOME
- 診療科のご案内
- 中央診療部門、管理運営部門など
- 医療安全管理部
医療安全管理部
基本理念
近年、医療技術の高度化・複雑化・高速化に加え、患者の高齢化も進み、大学附属病院にはより高い医療水準が要求されています。その中で実践される医療は、多職種協働でかつ複雑な連携を要し、他の産業システムと比較してもエラー誘発要因が非常に多いのが現状です。
医療安全管理の実践の上では、エラーの管理、医療の質の管理、医療紛争への対応と、これら三つが重要な基盤と考えられます。医療スタッフはこれらに迅速かつ適切に対応し、安全で良質な医療の実践に努めることが責務です。
医療安全管理部は、日々の診療業務の環境と安全を見つめながら、医療の安全と質の向上に関するスタッフの養成、ならびに安全で良質な医療システムの確立を日々目指しています。