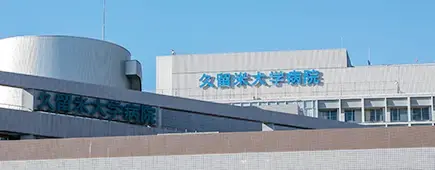久留米大学病院は、災害拠点病院として指定を受けています。水害や地震などの災害が起きたときに、地域を守る砦としての役割を担います。ヘリポートを有すること(当院はさらにドクターヘリも運用)、DMAT(ディーマット)と呼ばれる災害派遣医療チームがあること、停電時にも治療ができる自家発電機があること、水や物資の備蓄があること…など、いくつもの要件を満たし、万が一の事態に備えています。
筑後エリアの皆さまには、特に水害が身近な心配事かと思います。実際に久留米大学病院でも、2020年に筑後川の増水で1階の高度救命救急センターの入院患者全員の垂直避難を行いました。幸いなことに病院内に浸水はありませんでしたが、万が一に備えた救命避難は早めの対応が大切です。
そのため年1回は災害訓練を行うことも、災害拠点病院の要件の一つとなっています。災害はいつ起こるのかわかりません。いざという時に全職員が迅速に的確に行動できるよう、災害に備えた訓練は非常に大切です。当院でも毎年必ず、災害をシミュレーションした訓練活動を行っています。
2023.11.14
地域を守る「災害拠点病院」を知っていますか?
医療現場
地域の災害拠点病院に指定されている久留米大学病院。その取り組みについて、高度救命救急センターの副センター長・山下先生に話を伺いました。
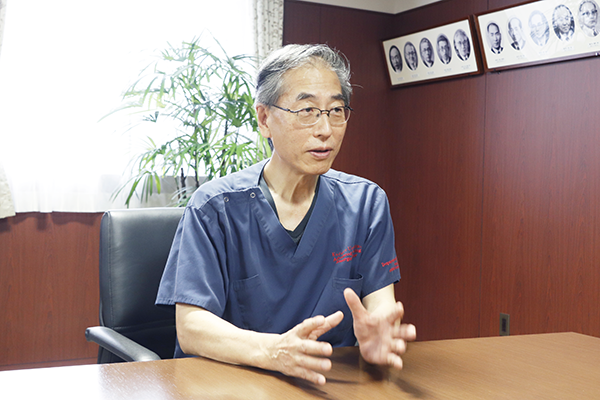
万が一の災害時に、地域の皆さまを守る“最後の砦”

他院の医師も驚く、大規模な災害訓練。

久留米大学病院では、2年前と一昨年は水害に備えた訓練を、昨年と今年は地震に備えた訓練を行いました。実際の災害時には医療機関だけでなく、消防署や自衛隊、自治体、警察など複数の組織との連携が欠かせません。そのため訓練時も関係各所との連携を前提として情報を共有。今回は、マグネチュード5~6.8を想定し、災害レベルごとに的確な行動ができるよう院内で訓練を行いました。当院のDMAT(災害派遣医療チーム)隊員も含めて、部門を横断し、幅広い職員を対象とした訓練です。
災害拠点病院に指定されている病院は地域ごとにいくつかあるのですが、今回は他院の医師も当院の訓練を見学に来てくださいました。これほど全科が協力して大規模な訓練を行っていることと、訓練の内容について、非常に参考になると言っていただきました。
災害時には現場もひっ迫し、予期せぬことが起こります。緊迫した状況でも迅速に対応できるように、日頃の訓練が大切なのです。これは当院のみならず、医療に携わる方々すべてに伝えたいことの一つです。
災害拠点病院に指定されている病院は地域ごとにいくつかあるのですが、今回は他院の医師も当院の訓練を見学に来てくださいました。これほど全科が協力して大規模な訓練を行っていることと、訓練の内容について、非常に参考になると言っていただきました。
災害時には現場もひっ迫し、予期せぬことが起こります。緊迫した状況でも迅速に対応できるように、日頃の訓練が大切なのです。これは当院のみならず、医療に携わる方々すべてに伝えたいことの一つです。
熊本の震災を経験し、多くの人に伝えたいこと。

私自身は、病院では高度救命救急センターの副センター長として災害に備え、大学では災害・危機管理担当の教授として、次代のDMAT(災害派遣医療チーム)として活躍できる人材の育成に力を注いでいます。 少し前の話になりますが、2016年の熊本地震の際には、私もDMATの一員として、最初の第一陣派遣で熊本に向かいました。大規模な災害時には、県内のみならず県外の災害拠点病院も連携し、ともに協力し合うことになっています。熊本地震の時は、久留米大学病院がドクターヘリの連絡担当基地病院となり、九州各地から熊本へのヘリ派遣を、安全かつ的確に運用するための司令塔となりました。
私が皆さまに伝えたいのは、自分の身を守るために普段から備えていただきたいということです。地震の際に家具が倒壊しないよう対策しておく、防災グッズを用意しておく、ご自宅の地域の避難場所と経路を把握しておくなど、平時でもできることはたくさんあります。いつ起こるかわからないことだからこそ、他人事と思わず、ぜひ普段から備えていただきたいと思います。
私が皆さまに伝えたいのは、自分の身を守るために普段から備えていただきたいということです。地震の際に家具が倒壊しないよう対策しておく、防災グッズを用意しておく、ご自宅の地域の避難場所と経路を把握しておくなど、平時でもできることはたくさんあります。いつ起こるかわからないことだからこそ、他人事と思わず、ぜひ普段から備えていただきたいと思います。